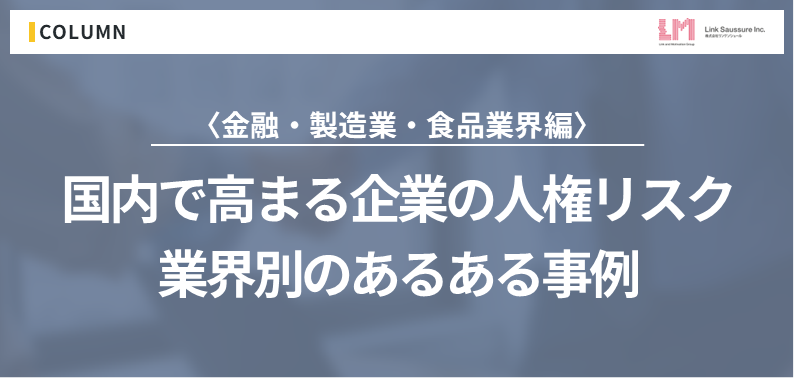
企業経営において「人権リスク」は避けて通れない重要課題となっています。
国連指導原則やESG投資の拡大を背景に、人権デュー・ディリジェンス(人権DD)の実践は上場企業を中心に急速に広がりました。
本記事では、金融・製造業・食品業界における典型的な人権リスクと事例を解説し、なぜ管理職調査だけでは不十分なのかを整理します。
さらに、リンクソシュールが提供する「人権DDデジタルサーベイ」を紹介し、全社的かつ継続的な人権リスク対応のあり方を提示します。
人権リスクとは?企業が直面する背景
近年、企業活動における「人権リスク」は、もはや一部のCSR担当部署のテーマではなく、経営全体を左右する重要課題となっています。
国連「ビジネスと人権に関する指導原則」の採択以降、企業の責任は自社の内部にとどまらず、サプライチェーン全体へ拡張されました。
さらに、ESG投資の拡大に伴い、人権デュー・ディリジェンス(以下、人権DD)の実践が国際的に求められています。
日本国内でも、政府による「ビジネスと人権に関する行動計画(NAP)」や人権DDガイドラインの策定、コーポレートガバナンス・コードの改訂をきっかけに、多くの上場企業が人権方針の策定や人権DDの導入を急速に進めています。
ここで重要なのは、「人権リスク」という言葉が指すものです。しばしば「企業が被る損害」と誤解されがちですが、実際には ライツホルダー(労働者、消費者、地域住民など)の権利が侵害される可能性 を意味します。企業にとって法務・レピュテーション・財務面での損害は「結果」に過ぎず、出発点はあくまで「権利を持つ人々の視点」にあるということです。
人権デュー・ディリジェンスの必要性と国内外の動向
国外では、すでに深刻な人権課題が企業の経営リスクとして顕在化しています。
たとえば、フランスの銀行BNPパリバは、スーダン政府の人権侵害に加担したとして約2万人の難民から訴訟を起こされ、2025年9月からニューヨーク連邦地裁で審理が予定されています。
このケースは「金融機関が直接行為をしていなくても、資金提供を通じて人権侵害に関与した」と見なされうることを示す象徴的な事例です。
製造業や食品業界においても、材料調達や委託工場での労働環境がしばしば問題視されてきました。紛争鉱物の使用、外国人技能実習生の低賃金労働、農場における児童労働など、国内外を問わず事例は後を絶ちません。
日本企業でも、形式的に人権方針を掲げるだけでは不十分であり、実務段階では次のような課題に直面します。
調査体制の構築:サプライチェーン全体をどうスクリーニングし、優先度を決めるか。
ステークホルダー対話:脆弱な立場の人々の声をどのように拾い上げるか。
苦情処理メカニズム:通報窓口を「設置」するだけでなく、匿名性や多言語対応を確保するか。
人権DDは「単発調査」ではなく、事業の変化に応じて継続的にアップデートされるプロセスです。そのため、企業単体での対応に加え、業界や地域全体での協働も不可欠になっています。
業界別のよくある人権リスクと構造的要因
金融業界の人権リスク
金融機関は直接人権侵害を行うわけではありませんが、投融資先を通じて人権侵害に関与する可能性があります。環境破壊や気候変動を加速させる事業、紛争地域で活動する企業への資金提供は、その周辺住民の生活や健康に深刻な影響を与えかねません。
情報収集が困難な点も金融特有のリスクです。特に紛争地域では現地調査が難しく、結果的に不十分な情報に基づいて投資判断が行われることがあります。
日本の事例では、三菱UFJフィナンシャル・グループが「赤道原則」に基づくリスク評価を実施し、
SOMPOホールディングスがリスクアセスメント結果を公開するなどの取り組みを進めています。
製造業(自動車など)の人権リスク
製造業、とりわけ自動車産業は、部品調達において「紛争鉱物」の利用が問題視されます。さらに、サプライヤー工場での児童労働や移民労働者への過酷な労働環境も大きなリスク要因です。
移民労働者が高額な紹介料を支払うことで債務労働に陥るケースも多く、こうした構造的問題に企業は責任を免れません。トヨタ自動車は「仕入先サステナビリティガイドライン」を策定し、サプライヤーと協力して改善に取り組んでいます。
食品・飲料業界の人権リスク
食品・飲料業界は、グローバルサプライチェーンが複雑であるため、強制労働や低賃金労働が発生しやすい業界です。特に農業分野では、15歳未満の子どもが危険な作業に従事している事例もあります。
日本企業の取り組みとしては、味の素グループが「多言語ホットライン」を設置し、花王が「人権DDデジタルサーベイ」を導入して定量的にリスクを把握するなどの例があります。
なぜ管理職調査や一部インタビューでは不十分なのか
人権リスクの全体像を正しく把握するには、管理職や一部担当者の声だけでは足りません。サプライチェーンの上流や現場の従業員、さらには地域住民など、脆弱な立場にある人々の声が見落とされがちだからです。
例えば、残業が「自己申告制」とされていても、実際には同調圧力や評価制度によって強制的に長時間労働が発生している場合があります。こうした問題は、管理職へのヒアリングだけでは可視化されません。
そのため、匿名性や多言語対応を備えたサーベイ、第三者を介した聞き取り、サプライヤー労働者の独立した相談窓口といった仕組みが欠かせません。
リンクソシュールの人権DDデジタルサーベイの特徴
リンクソシュールが提供する「人権DDデジタルサーベイ」は、従来の調査方法では見えにくかった人権リスクを網羅的かつ効率的に把握できるツールです。
26類型のリスクを網羅し、国際基準に対応
発生度+理解度の両面を調査し、根本原因を特定
全社員を対象とした全数調査が可能
改善まで伴走支援:eラーニング、経営層勉強会、サプライチェーン対応
さらに、SDGパートナーズ有限会社との協業やリンクアンドモチベーショングループの知見を活かし、診断から改善までを一貫してサポートする体制を備えています。
▼人権デュー・デリジェンスに関するご支援についてはこちら▼
その他の業界における人権リスク事例
-
IT・テクノロジー:AIのバイアス、プライバシー侵害(事例:Ericsson、ソニー)
-
建設・不動産:労働安全衛生、外国人労働者の権利、地域住民の立ち退き(事例:清水建設、三菱地所)
-
中小企業:ハラスメント、賃金未払い、差別(事例:アンサーノックス、現場サポート)
-
アパレル:低価格競争による強制労働や差別(事例:ワコールHD)
まとめ:人権リスクへの取り組みは全業界共通の課題
すべての企業は規模や業界を問わず、人権リスクを抱えています。その多くはグローバル化や効率追求といった構造的要因に根差しており、形式的な対応では持続的な改善は望めません。
人権DDを通じてリスクを可視化し、予防・軽減・救済のプロセスを実装することが、これからの企業経営における必須条件と言えるでしょう。
よくある質問
Q1. 人権リスクとは何を指しますか?
A. 人権リスクとは「企業が損害を受ける可能性」ではなく、企業の事業・製品・サービスによってライツホルダー(労働者・消費者・地域住民など)の権利が侵害される可能性を指します。その結果として、法務・レピュテーション・財務面で重大な影響を受けることがあります。
Q2. なぜ管理職へのアンケートや一部インタビューだけでは人権リスクを把握できないのですか?
A. 管理職調査では、サプライチェーンの上流や脆弱な立場の人々の声が拾えず、実態を見誤るリスクがあります。匿名性や多言語対応を備えたサーベイ、第三者による聞き取りなど、多様な声を直接収集できる仕組みが不可欠です。
Q3. 金融・製造業・食品業界でよくある人権リスクにはどのようなものがありますか?
A. 金融業界では投融資先を通じた環境破壊や紛争地域への資金流入、製造業では紛争鉱物や移民労働、食品業界では児童労働や低賃金労働が典型的です。これらは複雑なサプライチェーンや低コスト追求などの構造的要因に根差しています。
