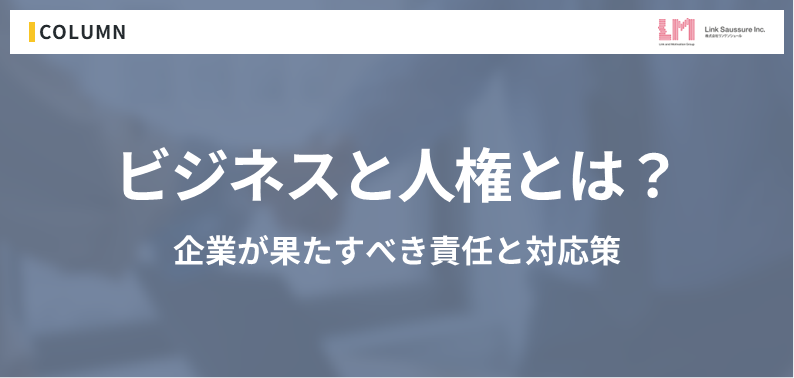
昨今、ビジネスシーンにおける人権問題が注目を集めています。サプライチェーンの中で人権侵害が生じている場合、消費者の購買が少なくなるだけではなく、企業の基盤を揺るがす大きな問題へと発展する可能性があります。本記事では、そもそもビジネスと人権の関係や企業が取り組む重要性、効果的な対応策についてご紹介します。
「ビジネスと人権」とは?
「ビジネスと人権」とは、企業が事業活動を行う過程で、すべての人の人権を尊重し、その侵害を防止・是正する責任を負うという考え方です。企業活動がグローバルに広がる中で、労働環境や児童労働、差別などの人権問題が注目されるようになりました。
ここでは、基本的なビジネスと人権の定義やなぜ企業で重要視されているのかについて解説します。
ビジネスと人権の定義
ビジネスと人権とは、企業が事業活動を行う際に、人権への悪影響を避ける責任を持つという考え方です。これは単に法令遵守を超え、自社だけでなくサプライチェーン全体においても、人権侵害を未然に防ぎ、対処することを求めています。
国連が策定した「ビジネスと人権に関する指導原則(UNGPs)」により明確化されたこの概念は、企業が人権侵害を予防・是正する義務を持つことを国際基準として示しています。
また、この考え方は企業の社会的責任(CSR)やESG(環境・社会・ガバナンス)とも深く関連しており、企業の持続的成長や長期的な価値創造に不可欠とされます。
投資家や消費者からの関心が高まるなかで、企業が人権尊重を積極的に推進することが求められています。
なぜ今、企業にとって重要なのか?
企業が今、「ビジネスと人権」に真剣に取り組むべき理由は、人権侵害を放置することが企業の社会的責任(CSR)に反し、同時に自らの事業活動を脅かす重大なリスクとなるからです。企業は、自社だけでなくサプライチェーンも含め、自らのビジネスが人権に与える影響を把握し、侵害リスクを防ぐ義務があります。これを怠れば、社会からの信用が失墜し、ビジネス基盤そのものが危機にさらされる可能性があります。
近年、企業が人権問題を軽視できない理由として、まず法規制の強化が挙げられます。EUの「企業持続可能性デュー・ディリジェンス指令(CSDDD)」をはじめ、日本政府も人権尊重に関するガイドライン策定を進めており、企業は国際的な法的責任を負う流れになっています。
また、投資環境も急速に変化しています。ESG投資の規模は世界的に拡大を続けており、投資家が企業の人権対応を重視する傾向が強まっています。人権侵害のリスクを管理できない企業は、投資対象として敬遠されるリスクが否めません。
さらに、消費者意識の変化も企業の対応を促しています。消費者は倫理的消費を重視し、サステナブルブランドを積極的に選択する傾向があります。人権侵害を起こした企業は消費者から支持を失い、市場競争力を大きく損なうでしょう。
このように、企業が人権問題を適切に管理することは、社会的責任を果たすという倫理的観点だけでなく、ブランド価値を守り、投資家や消費者からの信頼を維持するためにも極めて重要となっているのです。
企業が果たすべき「ビジネスと人権」の責任
グローバル化が進む現代において、企業は単なる経済的存在ではなく、社会に対する責任を果たす主体としての役割が強く求められています。特に「ビジネスと人権」という観点からは、企業活動が引き起こす可能性のある人権侵害への対応が国際的な関心を集めています。
サプライチェーンの拡大やアウトソーシングの一般化により、企業の影響範囲はかつてないほど広がっています。こうした中、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則(UNGPs)」をはじめとする国際基準や各国の法制度が整備されつつあり、企業は自らの活動が人権に与える影響を深く認識し、積極的に対応することが求められています。
「保護・尊重・救済」の3原則
「ビジネスと人権に関する指導原則(UNGPs)」は、企業と人権の関係において国際的に広く支持されている枠組みであり、三つの柱から構成されています。
第一の柱は「国家の保護義務」です。
これは政府が法律や制度を整備することにより、企業による人権侵害を予防・是正する責任を指します。たとえば、労働基準法の整備や人身売買防止法の施行などがこれに該当します。国家は企業活動の監視者としての役割を果たす必要があります。
第二の柱は「企業の人権尊重責任」です。
企業は、自らの活動やビジネス関係を通じて生じうる人権リスクを認識し、それを未然に防止する責任を負っています。この責任は、法律に違反していなくても問われる倫理的義務でもあり、企業のCSRやESG対応の中核を成します。
第三の柱は「救済へのアクセスの確保」です。
人権が侵害された場合に、被害者が正当な手続きを通じて救済を受けられる手段が存在することが重要です。企業は内部通報制度や苦情処理メカニズムを整備することで、信頼性ある救済の機会を提供する必要があります。
国際基準と国内規制の動向
企業が人権に関する責任を果たすためには、国際的なガイドラインや国内制度を理解し、これに沿った対応を行うことが求められます。
たとえば、OECD多国籍企業行動指針は、企業に対して人権を含むさまざまな分野での責任ある行動を促す国際的基準です。また、ILO(国際労働機関)が定める労働基準も、児童労働や強制労働の禁止などを通じて企業の人権配慮を促進しています。
さらに、国連の持続可能な開発目標(SDGs)とも密接に関連しています。特に「目標8:働きがいも経済成長も」や「目標12:つくる責任 つかう責任」は、企業が公正な労働環境の提供やサステナブルな供給網の構築に取り組む必要性を示しています。
日本においても、「ビジネスと人権」に関する国別行動計画(NAP)が策定され、企業による人権尊重の取り組みが求められています。さらに、近年は政府による公共調達における人権尊重の要件化も進みつつあり、民間企業にとっても人権への配慮が取引条件として求められる時代となっています。
企業が直面する人権リスク
現代の企業は、収益や成長だけでなく、社会的責任をどのように果たしているかという観点でも厳しい目が向けられています。特に「ビジネスと人権」というテーマは、サプライチェーンの拡大やテクノロジーの進展に伴い、企業活動と人権の関係性がますます複雑化している中で、避けては通れない重要課題となっています。
企業は今や、自社の枠を超えて事業全体が人権に与える影響を把握し、リスクを予防・是正する姿勢が求められています。人権リスクを見過ごすことは、企業の信用・ブランドを損なうだけでなく、法的責任や投資機会の損失にも直結しかねません。
事業活動による影響
企業が直面する人権リスクは多岐にわたり、事業活動のあらゆる段階に潜在しています。
まず、労働環境の悪化が挙げられます。長時間労働や低賃金、安全管理の不備などは、従業員の健康や生活の質を著しく損なう可能性があります。特に現場を担う労働者の権利が軽視されやすく、メンタルヘルスの問題や労災などを引き起こす原因となります。
また、サプライチェーン上の人権問題も深刻です。海外の製造拠点において、児童労働や強制労働といった非人道的な労働慣行が存在するケースは後を絶ちません。さらに、製造過程での環境破壊が地域住民の生活や健康を脅かすこともあり、企業の責任が問われる場面が増えています。
さらに、消費者や地域社会への影響も見逃せません。個人情報の不適切な収集・利用はプライバシー侵害につながり、デジタル化が進む中でそのリスクは拡大しています。また、製品の大量生産・大量廃棄が地域の環境負荷を高め、住民の健康や生活環境に悪影響を与えることもあります。
業界別の主なリスク
人権リスクは業種によって異なる特徴を持ち、それぞれに応じた対策が求められます。
製造業や小売業では、主にサプライチェーン上での労働搾取が問題視されています。低コストを追求するあまり、下請けや海外工場で過酷な労働環境が発生することがあり、企業ブランドの信頼を大きく損なう可能性があります。近年はサステナブルな調達の実現に向けて、取引先の人権状況を監査・評価する企業も増えています。
IT・テクノロジー業界では、データプライバシーの保護やAI技術の倫理的使用が大きな課題です。大量の個人情報を扱う中で、セキュリティや透明性が欠ければ、深刻な人権侵害につながりかねません。また、AIのバイアスや差別的なアルゴリズム設計は、無意識のうちに特定の集団の権利を侵害するリスクをはらんでいます。
金融業においては、ESG投資の拡大に伴い、人権配慮が投資判断の中核に位置づけられるようになっています。投資先企業が人権侵害に関与している場合、金融機関自身もその責任を問われる可能性があり、投資判断の透明性と倫理性が求められています。
企業が実施すべき具体的な対応策
企業活動がグローバルに広がるなかで、人権尊重の重要性はますます高まっています。人権侵害のリスクは企業の評判や信頼を大きく損なうだけでなく、投資家や消費者からの支持を失う重大なリスクにもなり得ます。こうした背景を踏まえ、企業には単なる理念としての人権尊重ではなく、具体的な行動としての対応が求められています。
国連の「ビジネスと人権に関する指導原則(UNGPs)」を基盤としながら、企業がどのようなステップで人権リスクを把握・対応し、持続可能な事業運営につなげていくのか。その鍵を握るのが、人権デュー・ディリジェンス(HRDD)をはじめとする実践的な取り組みです。
人権デュー・ディリジェンス(人権DD)の実施
企業が人権を尊重するうえで不可欠なのが、人権デュー・ディリジェンス(人権DD)です。これは、事業活動が人権に与える影響を事前に評価・予防し、継続的に監視・対応していくためのプロセスです。
まず重要なのがリスク評価です。企業は自社の事業領域全体を見渡し、労働環境、製品・サービスの提供方法、地域社会への影響など、どこに人権リスクが潜んでいるかを分析する必要があります。
次に、リスクが特定された場合には予防策の導入が求められます。具体的には、人権方針や企業倫理に関するポリシーの整備、従業員や関係者への人権研修の実施が挙げられます。これにより、組織内の意識改革と予防的行動が促進されます。
さらに、モニタリングと情報開示も重要です。定期的な評価と改善を繰り返すだけでなく、ステークホルダーとの対話を通じて、取り組みの透明性を確保することが信頼構築に直結します。
サプライチェーンの管理
企業の人権リスクの多くは、サプライチェーンの中に潜んでいます。したがって、サプライチェーンに対する人権デュー・ディリジェンスの実施は不可欠です。取引先や下請け企業においても、児童労働や強制労働、環境破壊などのリスクを洗い出し、改善を促すことが求められます。
また、倫理的調達の促進も効果的です。フェアトレード製品の採用や、環境・社会に配慮したサプライチェーンの構築を進めることで、企業は持続可能な価値提供を実現できます。サプライヤーに対するガイドラインや行動規範の策定と運用も、その一環として重要です。
ステークホルダーとの対話
企業が人権対応を強化するには、多様なステークホルダーとの対話が欠かせません。
たとえば投資家に対しては、ESG情報を盛り込んだレポートの開示などを通じて、企業が人権リスクをどう管理しているかを説明する責任があります。透明性のある情報発信は、信頼を高め、持続的な投資を呼び込みます。
消費者に向けては、エシカル(倫理的)なブランド構築が重要です。人権に配慮した商品やサービスは、消費者からの共感と支持を得やすく、企業価値の向上にもつながります。
従業員との対話も不可欠です。ダイバーシティ&インクルージョン(多様性と包摂)を推進し、誰もが尊重される職場環境を整備することは、従業員のモチベーション向上と組織の健全な成長を後押しします。
さらに、地域社会との信頼関係構築も企業の社会的責任の一部です。企業活動が地域の暮らしや環境に与える影響に配慮し、協働の姿勢で取り組むことが求められています。
リンクソシュールの支援
ここでは、当社リンクソシュールが行うビジネスと人権に関するご支援内容について詳しくご紹介します。
「人権DDデジタルサーベイ」による実効性の高い支援
当社が提供する「人権DDデジタルサーベイ」は、網羅的・効率的・本質的に実効性のある人権デューデリジェンスを実現するサービスです。
まず特徴的なのが、網羅性です。グローバルスタンダードの26類型人権リスクをすべてカバーし、人権リスクの「発生度」だけでなく、「理解度」まで調査することによる正確なリスクを評価することができます。
2つ目は効率性です。本社・グループ、一部サプライチェーンを含めた一括の全数調査が可能です。また、経年変化による持続的なモニタリングをすることにより、継続的かつサステナブルな人権デュー・ディリジェンスを実現します。
3つ目は本質性です。心理的安全性、アンコンシャスバイアス(無意識の偏見)の定量化により、リスクの根本原因を特定することができます。また、組織制度・風土の専門家による、実効的な企業変革・開示までワンストップで伴走します。
これらにより、表面的な対応ではなく、持続可能な人権デュー・ディリジェンスを実現します
まとめ:企業が果たすべき責任と次のステップ
企業が人権を尊重する責任は、もはや選択ではなく必須の経営課題です。国際基準に基づいた人権ポリシーの策定を出発点に、継続的なリスク評価と改善を伴う人権デュー・ディリジェンスの実施が求められます。加えて、サプライチェーン全体の監視と透明性の確保により、信頼性の高いビジネスの構築が可能となります。
こうした取り組みを効率的に進めるためには、デジタルツールの活用が有効です。また、投資家・消費者・従業員などとの対話を通じて多様な視点を取り入れ、より実効性のある対応を目指すことが、企業の持続的成長につながる次のステップとなります。
監修

代表取締役CEO
田瀬 和夫
1967年福岡県福岡市⽣まれ。東京大学工学部原子力工学科卒。
1992年外務省に入省。2001年より2年間、緒方貞子氏の補佐官として「人間の安全保障委員会」事務局勤務。
その後、国際連合事務局、デロイトトーマツコンサルティングの執⾏役員を務め、2017年9⽉に独⽴しSDGパートナーズを設⽴。
企業のサステナビリティ方針全体の策定と実施⽀援、SDGsの実装⽀援、ESGと情報開⽰⽀援、⾃治体と中⼩企業へのSDGs戦略⽴案・実施⽀援などをリードする。
また、2019年12⽉には事業会社であるSDGインパクツを設⽴し、実際に社会に持続的インパクトをもたらす事業へも参入。
さらに、2021年9⽉にはニューヨークのサステナブル・カフェ「Think Coffee」の⽇本誘致のためThink Coffee Japan株式会社を設⽴し、現在上記3社の代表取締役。私⽣活においては9,000人以上のメンバーを擁する「国連フォーラム」の共同代表理事
